|
80�N��L���_������90�N���ǂ�.4
����������T�O
�u���l�w���^�v�Љ�ɂ�����u�����^�v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���v�����I���K��\������В��@�Έ�a�Y
|
|
|
���t�B���^�[�Ƃ��Ắu�l�̌��v
|
|
|
�@����܂ŁA80�N��̑�O�_�_����U��Ԃ�A���ꂪ�s��̃_�u���E�C���[�W��������_���ł��������ƁA�����Ă��ꂪ�������������Ƃ��āA�����ł̌��T�O�̞B�������l�����邱�Ƃ����Ă��܂����B���̂��ߑO��́A���݂̌��T�O�m�����ׂ������ȉ��̎l�ɕ��ނ��܂����B
1.��������莩�����g�ł��낤�Ƃ���l�Ԃɂ���ĕ\�킳���A�^�̌��Ƃ��Ắu�����^�v��
2.��ʓI�A���ՓI�ڕW�Ɍ������ĂЂ����瓭��������l�Ԃ̎��A�c�����ɐe�ɂ���ăZ�b�g����Ă���u���@���w���^�v��
3.���l����̏��F��ړI�Ƃ������Ȃ̍��ى��ɂ��A�Љ�I�Ɍ��������L���Ƃ��Ắu���l�w���^�v��
4.���Ȓ��S��`�A��l�A�ϐl�Ƃ������u���̑������`�Ƃ��Ắv��
�@�ȉ��A���̂悤�ɕ��ނ��ꂽ���T�O���t�B���^�[�Ƃ��Ȃ���A��̘_����U��Ԃ邱�Ƃɂ���Ă��̘_�c�̐H���Ⴂ��_���W�J��̂˂���𖾂炩�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B
|
|
|
���w�V�u�K�w����v�̎���x�ɂ��������
|
|
|
�@�����q���i���A�����H�Ƒ�w�������j��10�����ŋL�����悤�ɁA�����w�V�u�K�w����v�̎���x�i85�N7���@���{�o�ϐV���Ёj�ɂ����āA����҂̌������s��̑��l���������炵���Ƃ���l������ے肵�Ă��܂��B�����Ă��̗��R�Ƃ��ď���҂̃O���[�v���������A����Ɂu�������g�������]�������A���l�������]���ɂ���Ė����������E�����B�܂�A���l�u���������킯�ł���v�Ƃ��ď���҂̑��ΓI�ȉ��l�ςƑ��l�u���������Ă��܂��B
�@������ے肷�闝�R�Ƃ��ꂽ����҂̌X���́A��������u���l�w���^�v���̑����ł��B�����āu���v������ƑΗ�������̂Ƃ��邱�̂悤�ȍl�����́A�`���I�l��`�ɂ��Ƃ������̂ł���A���Ɍ��炸�����Ȃ����ɑ��邲����ʓI�ȍl�����ƂȂ��Ă��܂��B�������u���l�w���^�v�Ɩ����ȁA���l�ς�C�t�X�^�C���̕s�ϐ�������Ƃ�����Ƃ́A���͌��݂̎Љ�ł͌������������Ȃ��Ȃ����u�����w���^�v���ɑ��Ȃ�܂���B����ɂ�������炸�Ȃ������E�̂悤�ȍl�����ő�������ƁA��O�ɂ��錻���̌������A����Ό��Ă������Ȃ��Ƃ�����ԂɊׂ�̂ł��B
�@���͏�f���̒��ŁA1979�N�̑����{���v�ǂ̎��������q���͂ɂ��������ʁA����̍������ɉe�����y�ڂ��Ă���̂����Z���Y�̑召�������Ƃ��Ă��܂��B�����Ă��̂��Ƃ��u�w�����x���́w�O���[�v���x�Ƃ́A���̂��Ƃ͂Ȃ�����҂̊K�w�������A�Ƃ������ƂɂȂ�B�v�i�����j�Ƃ������̎咣�𗠕t���Ă���Ƃ��Ă��܂��B
�@���̍ۂɁu�Z��E���ہE�t�@�b�V�����v�ɂ����ċ��Z���Y�̉e�����傫���A�u�����ԁE�y��E�X�|�[�c�p�i�E�I�[�f�B�I�E����E��Áv�ł͂��܂�W���Ȃ��Ƃ��Ă���̂ł����A���ӂ������̂͏��ɂ���ċ��Z���Y�̉e�����傫���Ƃ��ꂽ�O�҂́u�Z��E���ہE�t�@�b�V�����v���A�������70�N��ȍ~�A����҂������I�ɉ��o���邱�Ƃ��R�A��v���_�N�g�Ƃ��āA�r���𗁂юn�߂����i���Ƃ������Ƃł��B
�@���ؔ����i�����A�������`��w�������j�́A�w�f�U�C���̐헪-�~�]�͂�����x�i87�N8���@�u�k�Ёj�̒��ŁA�u�j���[�t�@�~���[�v����сu���C�t�X�^�C���v�Ƃ������t�̗��s���������珤�i���g�[�^���Ȑ����C���[�W�ƂƂ��ɔ�����悤�ɂȂ����A�Ƃ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�u�Ƃ�����w�����V���x�̋L���ɂ���Ƃ���A1970�N�㔼���납��A�ЂƂ��ƂŌ����A�������A�܂�Łw�X�i�b�N���x�i���ꂾ���Ƃ͌���Ȃ����j�ɁE���o�E���n�߂�w�ƒ�x���o�Ă����̂ł���B�w���C���x�Ƃ�������������o�����̂����傤�ǁA�������̂��Ƃł���w�����x��w�H�ו��x�܂ł��E���o�E����Ƃ����̂́A�����̏�ł���Ƃ��A���傤�Ǖ���̂悤�ɁA�Ƃ炦�n�߂�����ɑ��Ȃ�Ȃ��B�v
�@�����Ĕ��؎��́A���̂悤�Ɋ�{�I�ȗL�p���ɕt�����ꂽ�C���[�W�ŏ��i��I�Ԃ悤�ɂȂ�������҂́A�L���Ŏ�����邳�܂��܂ȃ��C�t�X�^�C����������̒��ł��������ϋq���ӎ������l���̂悤�ɐU�����悤�ɂȂ����Ƃ��Ă��܂��B
�@���؎��̕`�����̏���ґ��́A�܂��ɑ��l����̏��F�����߂Ď��Ȃ����ى������Ȃ����Ƃ̒�Ă��邢�����̃R�[�h�ւƓ�������Ă����u���l�w���^�v�̎p���̂��̂��Ƃ����܂��B
�@���Ȃ݂Ɂu���ہv���A������\���鏤�i�̈�Ƃ����錋���������̂��Ƃ�T�^�I�Ɏ����Ă��܂��B�܂���{�̌������������̂悤�ȍ����������悤�ɂȂ����̂́A���ꂪ������_���̂܂��Ő�������A�l�тƂ̏j�������肷���Ƃ����{���̎p���A�u�������₩�ɉ��o�������v�A�u��l���ɂȂ肽���v�Ƃ����E�̌����̗~���ɉ����Ă������炾�Ƃ������Ƃł��B
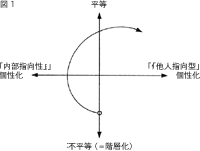 �@���̖��炩�ɂ����u�Z��E���ہE�t�@�b�V�����v�ɂ��������Ƌ��Z���Y�̑召�Ƃ̑��ւ́A�����̏��i�����ʉ��@�\�������Ă��邱�Ƃ������Ă���A����͂܂����̂悤�ȏ��i�ɂ�������̑ΏۂƂ��Ă̈Ӗ������o�����Ȃ��E�̌����̗~���̑��݂�������̂ł���܂��B �@���̖��炩�ɂ����u�Z��E���ہE�t�@�b�V�����v�ɂ��������Ƌ��Z���Y�̑召�Ƃ̑��ւ́A�����̏��i�����ʉ��@�\�������Ă��邱�Ƃ������Ă���A����͂܂����̂悤�ȏ��i�ɂ�������̑ΏۂƂ��Ă̈Ӗ������o�����Ȃ��E�̌����̗~���̑��݂�������̂ł���܂��B
�@�܂菬�̊K�w���������̂͏���҂̌�����ے肷����̂ł͂Ȃ��A�ނ��낻�������ɂ�����̂��Ƃ����܂��B
�@�}�P�́u���l�w���^�v����-�u�����w���^�v�����̎��ɕ����E�s�����i���K�w�����j�̎�������点�����̂ł��B�����̏o���_�͋ߑ�ȑO�̎���̏�ԁA���Ȃ킿�`���I�Љ�̂��Ƃł������ꂪ�������Ă��Ȃ���Ԃ������Ă��܂��B���̕��������݂̏ł���A�u���l�w���^�v�������s�[�N�ɋ߂Â�����A�܂��Љ�I�i������L��������Ԃ������Ă��܂��B
�@���̊K�w�������́A���̐�[�̓_�����ꂼ��̎��ɓ��e���ꂽ�_��ʌ̂��̂ƍl���A�������ߋ��́u�����w���^�v�������̊�ɂ��Č��݂̌�����ے肵���̂��Ƃ����܂��B
|
|
|
|
|
�@10�����Ŏ��グ���w����́u�B���O�v�x�Ɓw�u�V��O�v�̔����x�ɂ�������́A�s��ɂ���������̖������������]�����A�}�X�E�}�[�P�b�g�̌��݂Ԃ���������Ƃɂ���܂����A���̂��߂̍����Ƃ��āA��-7000��t�@�~�R���̃q�b�g���グ�����Ƃɂ͎��͌���I�Ȗ������܂܂�Ă��܂��B�����w�u�V��O�v�̔����x�̒��ŋ��E��Ȏ��i�����A������Ѓ��T�[�`�E�A���h�E�f�B�x���v�����g�В��j���u�v�V�I�ȋZ�p�́A���ꂪ�l�тƂ̎��Ȏ����̗~���ƌ��т��Ȃ�A�ے��I�ȉ��l�����̂ł���B�t�@�~���[�E�R���s���[�^�[����-7000���A�p�[�\�i���E���[�v�����A�p�u���A���̂悤�ɂ��đ�O�s����J���̂ł���B�v�Əq�ׂĂ���悤�ɁA�����͎������̑���ɑΉ��������i���Ƃ����܂��B���Ȃ킿�u���O�v�u���O�v�_�ɔ��_���鑤�́A����Ό�����ے肷��̂Ɂu�����^�v�����Ƃ����܂�����Ȃ������������Ă����Ƃ�����̂ł��B
 �@�R�萳�a���́A�w�_�炩���l��`�̒a���x�i84�N5���@�������_�Ёj�ɂ����āA���l�ς̑��l�����n�߂����݁A�l���A�܂��l�̑�����W�c�����̓����G��������K�v������Ƃ��A���̂悤�Ȏ���ɐ�����l�ɋ��߂���̂́u���l�ȑ��l�ɐG��Ȃ���A���l�����Ă������Ȃꂷ��\�́v�Ƃ��Ă��܂��B �@�R�萳�a���́A�w�_�炩���l��`�̒a���x�i84�N5���@�������_�Ёj�ɂ����āA���l�ς̑��l�����n�߂����݁A�l���A�܂��l�̑�����W�c�����̓����G��������K�v������Ƃ��A���̂悤�Ȏ���ɐ�����l�ɋ��߂���̂́u���l�ȑ��l�ɐG��Ȃ���A���l�����Ă������Ȃꂷ��\�́v�Ƃ��Ă��܂��B
�@�t�@�~�R���-7000�A���邢�̓f�B�X�j�[�����h��e���t�H���J�[�h�́A���̎R�莁�̎w�E�����i�ɂ����̂܂ܓ��Ă͂߂���ׂ����Ƃ������Ă��܂��B
�@���Ȃ킿���l�������n�D��~�������̓����œ��ꂵ�������i�A����������u�����^�v�����ɑΉ����������i�������݃X�[�p�[�q�b�g�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�����Ă��̂��Ƃ��u�����^�v�����̂��������Ôg�̂悤�Ȉ��|�I�Ȑ����������Ă���͖̂��炩�ł��B
�@�Ƃ��낪�w����́u�B���O�v�x�A�w�u�V��O�v�̔����x�̂�����ɂ����Ă��A��f�̋��E��Ȏ��̕��͂������Ă��̂悤�Ȍ����̐����͒�������Ă��܂���B�ނ���u�w���h�x���̂Ă����������v�i�w����́u�B���O�v�x���j�Ƃ����悤�ɁA����͖ڂ̓G�ɂ��炳��Ă���̂ł��B
�@�����̋K��Ɋւ��āA�w����́u�B���O�v�x�ł́u�l�Ɠ����������̂̓C�����Ƃ����u���v�Ƃ��Ă����ȒP�ɂȂ���Ă���݂̂ł��B���̕����ɂ���������́u���l�u���^�v�����ł��낤�Ɣ��f�����̂ł����A�S�̓I�ȗp�������͔��ɞB�����Ƃ����܂��B
�@�܂��w�u�V��O�v�̔����x�ł́A�t�ɏ㑺�����i�����A�������������ǒ��������j���������ɋ������肵�āA�u���̏ꍇ�̓J�������D���ł�����A�J�����ɂ��Ă͕��O�ł����ĂȂ�ׂ��l�̎g��Ȃ��悤�ȃJ���������Ǝv���B������~�m���^��-7000�͓��������܂��Ǝv���Ă���킯�ł��B�v�Əq�ׂĂ���悤�ɁA�����̓}�j�A�b�N�Ȏu���ƍl�����Ă��܂��B���̃}�j�A�b�N�Ȏu����D�E���[�X�}���́u�E�l�����v�ƌĂсA����ł��ꂪ�����Ă���u���E�I���ꉻ�v�ɏI���\�����w�E���A�u�E�l�I�ȋZ�\��ʂ��āA�����������߂�X���v�Ƃ��Ă��܂��B�㑺���ɂƂ��Ă̌������u�����^�v�����Ɓu���l�u���^�v�����ɂ܂������Ă���A�����ɂ������I�Ȃ̂ł����A���̂悤�Ɍ������������x�Ȃ��̂Ɍ��肷�邱�ƂŁA�~�m���^��-7000�̃q�b�g�̔w��ɂ���u�����^�v�����̗��ꂪ��������Ă���̂��Ƃ����܂��B
�@���̂悤�ɃX�[�p�[�q�b�g���̂��̂ɂ���Ă��̔w��ɂ���u�����^�v�����������Ȃ��Ȃ�̂��A���́w�V�u�K�w����v�̎���x�ɂ��Ďw�E�����A�����u���l�u���v�ƑΗ�������l�����̍������ɂ����̂Ǝv���܂��B
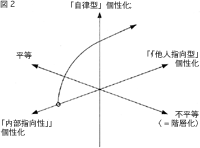 �@�}�Q�͐�̐}�P������Ɂu�����^�v�����̎�������点�����̂ł��B�����͂��̎��̉����点���ɉ��㏸���Ă��܂��B �@�}�Q�͐�̐}�P������Ɂu�����^�v�����̎�������点�����̂ł��B�����͂��̎��̉����点���ɉ��㏸���Ă��܂��B
�@�E�ɂ������A�u�����^�v�����������Ȃ��ł����Ԃ́A���̎��ɋC�Â��Ȃ��ł����Ԃ��Ƃ����܂��B
�@�����̂��Ƃ́A�w�_�炩���l��`�̒a���x�̎�肪�����������Ƃ�����A�u���l�u���^�v�Љ�ɂ�����u�����^�v�����Ƃ͉��Ȃ̂��A���邢�͂����ɂ���ׂ��Ȃ̂����A�L����}�[�P�e�B���O�ɂ����Ė��m�ɉۑ�Ƃ����ׂ����Ƃ��Ӗ����܂��B
�@�����܂ł́A�u���O�v�u���O�v�_�ɔ��_���闧��ŗp����ꂽ�u���v���d�������邱�Ƃɂ���āA���̘_���̕����̌����̈���A���̗p�������̞B�����ɂ��������Ƃ����Ă��܂����B���������̘_���̍ċᖡ�ɂ����Ă��ł����Ƃ����ׂ��Ȃ̂́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA���̘_���̔��[�ƂȂ����u���O�v�u���O�v�_���g�́u���v�̗p�����ɑ��Ȃ�܂���B�ނ���B�������B������U�����Ă������ƌ���ׂ��Ȃ̂ł��B�����Ŏ��Ɂw�w���O�v�̒a���x�ɂ����鎩�����̈��������ᖡ���邱�Ƃł����ɂǂ̂悤�Ȗ�肪�������������Ă��������Ǝv���܂��B
|
|
|
���u�����^�v�����ɂ����鐳���̕�����
|
|
|
�@�w�u���O�v�̒a���x�ł́A�u���O�v�ɂ��āA�u�ώ��ȑ�O�Љ�́A����ɕ��A���I�A���l�I�ȉ��l�ςԌʓI�ȏW�c�����܂�������B�u���O�v�̒a���ł���x�Əq�ׂĂ���悤�ɁA����́A�l�тƂ̌����A���l���ɑΉ�����T�O�Ƃ��ēo�ꂵ�܂����B
�@���̂悤�Ɍ����A���l��������Ƃ���u���O�v�Љ�Ɋւ��A�u�G���[�g�ւ̐ڋ߉\���v�Ɓu��G���[�g�̑��c�\���v�̓ŎЉ��ތ^�������R�[���n�E�U�[�̐}�������ƂɁA�u���͂�A�l�͗e�Ղɓ����Ȃ��B�w���삳��ɂ������O�̎���x�ɂȂ����̂ł���B�v�A�u��X�̌�����O�Љ�番�O�Љ�ւ̓]���́A�܂��ɑ����I�Љ���������Ƃ��Ӗ����Ă���B�v�Ƃ��āA���́u���O�v�Љ�A���O�̑���̂���ɂ����Ƃ����_�ɂ����āA�R�[���n�E�U�[�̑����I�Љ�ƈ�v����Ƃ��Ă��܂��B�܂������I�Љ�̓����ł��鎩�����ɂ��Ắu���O�̎���ɑ��鎩���I�l�ԂƂ����}���́A�ɂ߂Ĕ[���������B�v�Ƃ��Ă��܂��B
�@�����̂����̌�����������ƁA�u���O�v��a���������v���Ƃ����A�l�тƂ̌����A���l���ɂ́AD�E���[�X�}���̗ތ^�Ɋ�Â������̕��ނŌ����A�u�����^�v���������̂܂ܓ��Ă͂܂邩�̂悤�ł��B�Ƃ��낪�����́A����ł́u�����I�Ƃ��������M�������Ă�������̗p��́A���O�����ɂ͎�����Ȃ��B�����Ɗ����I�ȑ��݂ł��邱�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B�v�Ƃ��āA���̎�������ے�������Ă���̂ł��B
�@�����Č��ǁA�u�������Ȃ��Ƃ��A���O�́A��O��莩���I�Ƃ܂ōs���Ȃ��Ă��A�w�����x�I�ł��邱�Ƃ͊m���ł���B�v�Ƃ��āu�����v�I�Ƃ������t�Ɂu���O�v�_�̌��T�O���W���Ă��܂��B�������A���̌��t���̂̂���ȏ�̐����͂Ȃ���Ă��炸�A���̈Ӗ��͖��m�Ƃ͂����܂���B�܂��������ɂ��Ă��u�����I�Ƃ��������M�������Ă�������v�Ƃ������j�T�O�I�K�肩��A���́u�����u���^�v�Ƃ̍�������������A���������Ă����ł́u�����M�v���u���ՓI���l�v�ɒu����������ׂ��ł��낤�Ǝv���܂��B���������̂��Ƃ������ɂ����鎩�������̂̑��������s���m�Ȃ��߂ɖ��炩�Ƃ͂����܂���B
�@�������͂����肵�Ă���̂́A�u���O�v�͉����Ȃ�ł������I���݂ł���A�����ɃA���`�����I���݂��Ƃ����_�ł��B����͐�̐}2�Ō����u�����^�v�����̎��ɂ����鐳�����ɑ���t�s�Ƃ����܂��B���������̂��Ƃ́u�z���E�N���A���X�v�ɂ���Ď������𐳖ʂ���Ƃ炦���͂��́w����Ȃ�A��O�B�x�ɂ����Ă��܂����������ł���A���̘_���̍ő�̖��_�������ɂ������̂��Ƃ����܂��B����͂��́u�����^�v�����̎��ɂ����鐳�E���̕������m�ɂ��_���S�̂����Ă��������Ǝv���܂��B
|
|