|
80�N��L���_������90�N���ǂ�.6�@�ŏI��
�v�l�Ɗ����̓����ɂ�����҂́u�����^�v�����ւ̑Ή�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���v�����I���K��\������В��@�Έ�a�Y
|
|
|
|
|
�@�O��i1�����Łj�A�w�u���O�v�̒a���x�i�����������������ҁj�̕t�}�����グ�A���C�t�X�^�C����w���́A�����Ȃǂ̑g�ݍ��킹�ɂ���ĉ������ꂽ�u���v�Ƃ��Ắu���O�̊�v�́A��������ۂ̌l�̎��R�Ƒ��e�ꂸ�A���������Ă���͌��݂̎s��ɂ��������ґ�������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ������܂����B
�@�ނ��덡���̌l�̂��肩�����炷��A���̖�����D�݂̑g�ݍ��킹�̑����Ƃ��Ắu���v�́A���̂悤�Ȏs��S�̂̎p�Ƃ��Ă����A�����ɂ��������҈�l�ЂƂ�̎��Ȃ��̂��̂̎p�Ƃ��čl�����ق����s��̎��̂ɑ����Ă���Ƃ����܂��B
�@���Ȃ킿�����̎���́A������D�݂Ȃǂɂ���ċK�肳���o���G�e�B�̈�Ƃ��Ắu1/���v�ł͂Ȃ��A�ނ��낻�̋t���Ƃ��ĕ\�킳���ׂ����Ƃ������Ƃł��B
�@��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA����́u���l�w���^�v�Љ�ł́A���͌������ꂠ���L���Ƃ��đ��݂��Ă��܂��B���̏ꍇ�A���́A�������݂��ɑ��l���ӎ������������鋕�\�ł���A�������������������Ȃ�l�Ԃł����āA�ǂ̂悤�ȍ˔\��\�͂������Ă���̂��Ƃ������Ȃ̖{���I�ȉ\���͂����]���ɂ���܂��B
�@E�EH�E�t�����́A���\�I�Ɍ������ꂠ�������A���v�Ƃ̊W�ʼn��l�̌��߂���A�s��̏��i�Ƃ܂������������̂��Ƃ��āA���̂悤�ȏ̂��ƂŐ����鎩�ȑa�O�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�u���̂悤�ɂ��Ĕނ̓��ꐫ�̊���͂��̎��ȑ��d�Ɠ������s�m���ɂȂ�B������́A�l��������������̑��v�ɂ���č\������邱�ƂɂȂ�B���Ȃ킿�w�����͑��̐l�̋��߂�ʂ�̂��̂ł���x�Ƃ������ƂȂ̂��B�v�i�w�l�Ԃɂ����鎩�R�x�@�J�����V���E������Y����@�����n���Ёj
�u������������̑��v�ɂ���č\�������v���ȂƂ́A����������u������������̑��v�v�ɂ܂ŕ��A�������������Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł���͂��ł��B���������̎��ȂƂ́A����ɍی��Ȃ����Ă������Ƃ��\�ȋ��\�̎��ȂȂ̂ł��B
�@�E�̕��͂ɑ����ăt�����́A���i���������ɂ͗��s������A���̂��߃}�X���f�B�A��ʂ��Ď������X�^�[��f���̌����M�S�ɖ͕킳��Ă��邱�Ƃ��w�E���܂����B���̂��Ƃ́A�}�X���f�B�A�������Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂɔ���I�ɔ��B���������̎Љ�ɂ����ẮA����ɏd�v�ȈӖ��������܂��B
�w�l�Ԃɂ����鎩�R�x�̏o�ł��ꂽ�����̐l�тƂ��}�X���f�B�A�Ƃǂ̂悤�Ɋւ���Ă��������A���傤�ǂ��̂���Ȃ��ꂽ�AD�E���[�X�}���́w�Q�O�̊�x�i���O���Y�E�v�\������@�T�C�}���o�ʼn�j�Ɍf�ڂ���Ă���ʐڒ������炤�������m�邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���Ȃ킿1940�N�㖖����̃A�����J�̐N�������ڐG���郁�f�B�A�́A�T�Ɉ�x����x������ȉ��A�����Ă��T�ɓ�C�O�x���x�ςɍs���f��ƃ��W�I�i����͖����j����Ȃ��̂������̂ł��B
�@����ɑ��č����̓��{�̐N�̃��f�B�A�Ƃ̐ڐG�́A�e���r��W�I�A���邢�͖���{���܂߂��G���Ȃǂ̐����ւ̖������������Ď������Ƃ��ł��܂��B
�@�����Ă��̂悤�ȑ��푽�l�Ȕ}�̂ɂ�����h���}��L�����痬��o�Ă��閳���̌���C�t�X�^�C�����A�u���A���e�B�̋t�]�A���邢�͋L���E�C���[�W�ɂ������ȃ��A���e�B�����m����z���͂̏o���B�u���E���ǂƂ����Đ����u�ɂ����ċt�]���N�����Ă���B�v�i�w��ҕ����l�ފw�x�@������@�������Ёj�Ǝw�E�����܂łɎ������A����I�ȉe���������̐N�ɋy�ڂ��Ă���킯�ł��B
�@�����Ă��́A���C�t�X�^�C������̑��l���̖����A����ɓ��{�̎Љ�̂��܂��܂Ȗʂł̋}���ȍ��ۉ��ɂ��e�������܂߂��A���傫�Ȋϓ_���猩��Ƃ��A���̔����I�̊Ԃɂ������{�l�̃p�[�\�i���e�B�ɋN�����d��ȕω��̈�����炩�ɂȂ�܂��B���Ȃ킿���̔����I�����ɔ�Ⴕ���A���Ȃ̕��邢�͕������̔����I���i�ł��B
|
|
|
|
|
�@�����ɕ��A�������������ȂƂ́A���߂ɏq�ׂ��u���v�Ƃ��̏���҂̎p�ɂق��Ȃ�܂���B
�u�C�̕��q�̂悤�ɕ��V�v�i�w�u���O�v�̒a���x�j���Ă���̂́u�l�тƁv�ł͂Ȃ��A�������������Ȃł���A���̂悤�ȏ�ԂƂ́A�A�C�f���e�B�e�B������ӂ�ɂ���A���݊����ɂ����A�����̎���̂�������̂��̂Ȃ̂ł��B
�@���������Đ�́w�u���O�v�̒a���x�̕t�}�́A�u���l�w���^�v�Љ����l�Ԃ��A���̂悤�Ȏ��Ȃ̎p���}�[�P�b�g��ɉf���o�������̂ƌ��Ȃ������Ƃ��ł��܂��B
�@�Ƃ��낪�A��������Ƃ��̕t�}�͕ʂ̂܂������V���ȈӖ��������ƂɂȂ�܂��B�܂肱�̕t�}�ɂ�����A������D�݂̑g�ݍ��킹�ɂ���ċK�肳���u1/���v�́A����ɂ���Ă���l��W�c�����肳���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���܂��܂ȏ�ʂɉ����Ď��䂪����������ł��낤���\�̌��ɑΉ����Ă���̂��Ƃ������Ƃł��B
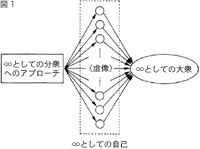 �@����͂܂��A�͕킳���ׂ������Ƃ��āA�s��̂Ȃ��ɔ×����Ă��鋕�\�̌��ɂ��Ή����Ă���킯�ł��B �@����͂܂��A�͕킳���ׂ������Ƃ��āA�s��̂Ȃ��ɔ×����Ă��鋕�\�̌��ɂ��Ή����Ă���킯�ł��B
�@�ȏ�̂��Ƃ��玄�́u���O�v�_�����̂悤�ɍl���܂��B���Ȃ킿����́A�����̋����Ƃ��Ă̌���C�t�X�^�C������A�֊s�̞B���ȁA�������l�̎�����ђʂ��Ă��̔w��̏W�c�S�̂ɓ��������邽�߂̎�@�ł���A���̏W�c��������O�ƌĂ��ׂ��A�u���v�Ƃ��Ă̋���ȏ���W�c�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B�i�}�P�j
�w�u���O�v�̒a���x�ł́A�}�[�P�^�[�̂�����ɂ��āA�u�����̍s�������X�⎩���̔����������m�����悢�v�Ƃ��A���̗��R���A�����̎s��ł́u���ʈ����j�[�Y�v�ɂ�����āu�f�����j�[�Y�v���d�v�ɂȂ��Ă������炾�Ƃ��Ă��܂��B
�@�������ɁA�����̐������Ɋ�Â��đn������Ƃ���������́A�}�[�P�e�B���O�݂̂Ȃ炸�N���G�C�e�B�u�����ɂ����Ă�����߂ďd�v�ȍ�@�ł��B�������A���̂悤�ȓƑP�I�Ƃ��v������@�������̃r�W�l�X�ɂ����Đ��藧������̂́A���܂��u�f�����j�[�Y�v�̎��ゾ����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�t�Ɍ����ȈӖ��ł́u�f�����j�[�Y�v�ȂǑ��݂��Ȃ����ゾ����Ȃ̂��ƍl����ق������炩�ɘ_���I�ł��B
�@�ȏ�A�u���O�v�_���{���I�ɏ]���ʂ�̑�O���^�[�Q�b�g�ɂ����l�����ł��邱�Ƃ������g���b�L�[�Ȋ����̂���q�ו��Ŏ����Ă����̂ł����A����́A�����u���O�v�_�����̌��t�ʂ�Ɏ���Ĕᔻ����Ȃ�A����͂܂��Ɂu�Ɍ��I�ȁv�w���ى��x�헪���v�i�w�u�V��O�v�̔����x�@TBS�������ҁj�Ƃ������ƂɂȂ�̂ɑ��A���͂��̂��Ƃ������ڂɂ������A�u���O�v�_�̖{���͂����ɂ͂Ȃ��A�����܂ł���O���Ȃ�Ƃ����삵�悤�Ƃ���_�ɂ���̂ł����āA���̗L���������E�����̂悤�Ȗ{�����琶����̂��Ƃ������Ƃ��������߂ł����B
�@�܂��l�̐��������Ƃ������������n�����̌���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�u���O�v�_�݂̂Ȃ炸�����_�I�l�����������Η����I�Ȃ��̂�ے肷�鍪���Ƃ��Ă����_�ł����A�E�̂悤�ɍ����̎���̂�������l����A���̂悤�Ȑ��������t�ɂ�蕁�ՓI�Ȃ��̂ɂȂ����Ă��邩�炱���A�n�����̌���ł��肤��̂��Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ�킯�ł��B
|
|
|
�����Ȃ̑��l���Ɓu�����^�v����
|
|
|
�@���C�I�l���E�g�������O�́A����l���{���̎��Ȃ����߂Ă�܂Ȃ��͉̂E�̂悤�Ȏ��Ȃ̕������╪��ɂ���Ă����炳��鎩��r��������̂��߂��Ƃ��A���̂悤�Ȏu�������ɓI�ɉ������߂Ă��邩���������Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�u�����I�����̈̑�Ȍ|�p�^���̐���䂫�����Ă���ƁA�s�ق���́t�gauthentic�h�Ƃ������t�̃M���V�A�̑c��̒��ɖ����ɂ��錃��ȈӖ��̂��Ƃ������o���B�gAuthenteo�h�Ƃ͏\���Ȏx�z�͂����Ƃ������Ƃł���A�܂��E�l��Ƃ��Ƃ����Ӗ��ł�����B�gAuthentes�h�Ƃ͗B�P�Ɏ�l�ł���s�҂ł���Ƃ��������łȂ��A���Q�ҁA�E�l�҂̈����ł���A����ɂ͎��E�ҁA���E�̈Ӗ��ł�����B�v�i�w�q�����r�Ƃ́q�ق���́r�x�쓇�G����@�}�����[�j
�@����ɂ���āu�ق���́v���A���p�i�⍜���i���A�Ȃ�̈Ӗ����Ȃ��܂�Ȃ����̂Ɏ���܂ł͂قƂ�Nj����I�ɋ��߂��邱�Ƃ̗��ɂ���{���̈Ӗ���m�邱�Ƃ��ł��܂��B�����āu�ق���́v�Ƃ������t�������ɐT�d�Ɏg���˂Ȃ�Ȃ�����������̂ł��B
�@�����A���Ȃ̋��͂܂��܂��[�������Ă���A���̂悤�Ȏ��ɎЉ�A��ɏq�ׂ��u�������v�����ɂ����镉�̕������Ɍ������ʂ������Ƃ́A������x�s��I�ł���̂�������܂���B
�@����������ł͐l�Ԃ́A���̂悤�Ȏ���ł��邩�炱���A�u���l�����čs�����Ȃꂷ��\�́v�i�w�_�炩���l��`�̒a���x�@�R�萳�a�@�������_�Ёj�ɂ���Ă��̎������傳���Ă����̂ł��傤�B
�@�R�莁�́A���̂悤�Ȏ���ɂ����鐬�n�����l�̎p���u������ꂽ�������̖��̔w��ŁA�˂ɐÂ��ɐ��߂Ă���o�D�̐S�̓��ꐫ�v�i�����j�Ƃ��ďq�ׂĂ��܂��B
�@���̂悤�ȁA���\�̎��Ȃ����\�Ƃ��Č���A���Ȃ킿���\�̋��\���Ƃ���������́A�}��������������[��L�����x���E�X�[�v��f�ނɂ����A���f�B�E�E�H�[�z���̈�A�̍�i�̌����ɒʂ��邩������܂���B�܂肻����ς���̂́A���\�̋��\���ɂ���āA�}�C�i�X�Ƀ}�C�i�X��������ƃv���X�ɂȂ�悤�ɁA�����������Ƃ��Č��Ȃ��瓯���Ɍ������𗧂��Ԃ��Ă���̂ł��B
�@���̘A�ڂ̏��߂ɏq�ׂ�����҂̗������Ƃ������ۂ́A���̂悤�Ȏ���̐��n�ɂ���Ă����炳��Ă���ƍl������ׂ��ł��傤�B�܂�L���ɖ�炳��Ă��邩�̂悤�Ɍ��������҂��A���͂��̏��i���A�E�H�[�z���̃L�����x���E�X�[�v���ς�悤�ɐ��߂ςĂ���̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�����ł���Ƃ���Ȃ�A���Ƃ��L���͖ʔ������肳����������Ƃ����A����������_�ɋ��ʂ���咣�́A����҂����̍L����ʔ������Ă��鑤�ʂ��������āA�����ɂ��̖ʔ������̂����\�����Đ��߂Ă�����Ƃ����A������̑��ʂ͌��Ă��Ȃ��咣�ł͂Ȃ����ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�@���̂悤�ȍL���̍ł��T�^�I�ȗ���A���ẴG���}�L�g�J�Q���g�����~���[�W���̍L���ɋ��߂邱�Ƃ��ł��܂����A���������ɑ����̍L�������܂��ɂ��̂悤�Ȍ��Ƃ܂����������Ƃ͌�����܂���B
|
|
|
|
|
�@���̂悤�ɂ��āu�����^�v�����ɂ����鐳���̗��������́A�݂��ɋt�����ɐi�ނ��̂ł���Ȃ��炻�̍��͂܂��������ꂾ�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B���Ȃ킿�܂����Ȃ̑��l��������A���ꂩ�琳���́u�����^�v�������i�W����Ƃ������Ƃł��B�����Ă���ɂ���ĕ������ւ́u�����^�v�����ł��鎩�Ȓ��S���Ȃǂ��A���炽�߂Ė{���̌��������s���A�������`�ɉ߂��Ȃ��ƌ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�@���̂悤�ȁu�����^�v�����̋t���I�ȕ\�����́A�l�̓��ʂɂ����Ă��A�Љ�ɂ����Ă����邱�Ƃ��ł��܂��B����݂̂łȂ����̍ł��s��Ȍ`�������̋��\�A�Ⓦ�������ɂ����Ēm�邱�Ƃ��ł���Ƃ�����ł��傤�B
�@�����̍��Ō��N���Ă��邳�܂��܂Ȍ`�̖����Ԃ̕�����Η��́A�����X�̎咣���v�����ɐ����Ȃ��̂ł����Ă��A�����ɑލs�������ʂ������Ă��邱�Ƃ��ے�ł��܂���B
�@���̂��Ƃ��炱�̂悤�ȕ�����Η��̔w�i�ɁA���������������Ȃ��ł������炳��Ă���ł��낤�l�̓��ʂ̊�@�𐄑����邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�@�����ɖ��剻��l�̊J�����i�ނƓ����ɁA�Љ�I��@�����傷��Ƃ����w�������W�̗��R�����邱�Ƃ��ł��܂��B
|
|
|
���u�����^�v�����ƍ���̍L��
|
|
|
�@�Ō�Ɂu�����^�v�������}���ɐi�W������Ȃ��ŁA�L�����܂߂��}�[�P�e�B���O�R�~���j�P�[�V���������ア���ɂ���ׂ����ɂ��čl���܂��B
�@�����Ŏ咣����̂́A�v�l�⊴�����L�@�I�ɓ�������A����炪�݂��ɑ�����ʂ����悤�ȁA����҂̗������ɑΉ������i���̎d���ł��B���̂悤�ȑi���̗L�����͑i���Ώۂ̐��n�x�ɔ�Ⴕ�Ă���A�K�R�I�ɂ��̔N��Ƃ����ւ��邱�Ƃ͖��炩�ɂ���Ă����K�v������܂��B
�@A�EH�E�}�Y���[�́A���Ȏ��������l�Ԃɑ��Ă͍L�������̎�@�����{�I�ɉ��߂˂Ȃ�Ȃ��Ƃ��A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�u���Ȏ����I�l�ԂɂƂ��āA������ڋ߂�A�����Ăȕ�V�Ȃǂ́A�������ɏd�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B���ʂ̂����ɂ��L���ł́A�����炭���̐l�����ɑ��Č��ʂ��Ȃ��ł��낤�B�����ĂȘA�z��Ќ��Î��A�����I�A�s�[���A�Ӗ��̂Ȃ��P���Ȕ����Ȃǂɂ͂قƂ�Ǔ�������ɂ����B���̂悤�Ȃ����͂������ċt���ʂނł��낤�B�܂�A�w���ӗ~���N��������̂ł͂Ȃ��A�t�Ɏ��킹��̂ł���B�v�i�w�l�Ԑ��̐S���w�x�@�������F��@�Y�Ɣ\���Z����w�o�ŕ��j
�@���̃}�Y���[�̎w�E�����̂܂܌��݂̍L���ɂ��Ă͂߂邱�Ƃ͂ł��܂��A����̍L�����l����ۂ̉����w�W�Ƃ����ׂ����̂ł͂���͂��ł��B
�@�����Ă��̂悤�ȉߓx�I�ȏɂ����āA���̃��[�X�}���̏q�ׂ����e�͂���߂ďd�v�ȈӖ��������܂��B
�u���Ƃ��Ă͎�̌����Ƃ����̂͂��ꎩ�g�z���āA�܂����������������̂ɂȂ�ɂ������Ȃ��ƍl�������̂��B�����āA���l�w���^�̐l�Ԃ̎������̔��W�͂܂��ɂ�������n�܂�̂ł���B�v�i�w�ǓƂȌQ�O�x�@�ߓ��p�r��@�݂������[�j
�@�����Ă��̂悤�ȈӖ��ł́A�����̏���҂����łɌ��R�~�̏��ʂ��ď��i���𑽊p�I�Ɍ���������悤�ɂȂ��Ă���A�s��ɂ��������҂̃v���V���[�}�����n�܂��Ă���Ƃ����_�����ڂ���܂��B
�@���̂悤�ȏœ��ɏd�v�Ȗ��ɂȂ�̂́A��Ƃ��s�Ȃ����܂��܂ȃA�v���[�`�̓��e�𑊌݂ɂ����Ɉ�v�����邩�Ƃ������Ƃł��B�����Ă��̂��Ƃ́A����܂Ő��i���̂��D�ꂽ���̂ł���Ȃ��珤�i�Ƃ��ď\���Ȑ��������߂邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������̂̑������A���̂悤�Ȉ�v�Ɏ��s���Ă��邱�Ƃɂ���ė��Â��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���Ƃ��ΑO�ɂ������u�V�e�B�v�i�z���_�j�̏ꍇ�A�u�V�����x�[�V�b�N�J�[�v�i�w����́u�B���O�v�@���o�r�W�l�X�ҁj�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���\�̗D�ꂽ�R���Z�v�g������Ƃ܂������قȂ��Ă������Ƃɂ���Ĕ���s���̕s�U���������Ƃ�����肪�������܂��B���邢�͂���Ƃ܂��������������u�}�[�`�v�i���Y�j�̏ꍇ�ɂ����Ă͂߂邱�Ƃ��ł��܂��B
|
|